
個人的に住宅の性能で一番重要視したのが地震に対する建物の信頼度。
地震大国日本にあって、個人的に絶対に外せない性能だった。
戸建を検討し始めると、必ずと言っていいほど耳にするのが、「耐震等級」というキーワード、
耐震等級は1から3まで基準があり、以下のような基準があることが分かった。
日本の耐震等級の基準
耐震等級1
建築基準法が全ての建物に求めている最低基準と同等の耐震性。
数百年に一度発生すると想定される震度6から7相当の地震に対して倒壊、崩壊しないこと。
耐震等級2
耐震等級1の基準に対して、1.25倍の耐震性。
学校や病院など避難所として使えるレベルの性能。
耐震等級3
耐震等級2の基準に対して、1.5倍の耐震性。
警察署や消防署など防災の要となる建物と同レベルの性能。
マイホームを検討している段階で、この等級制度を知ってからは、耐震等級3で建てることは自分のマスト要件になった。
また、これに付随する情報として知ったのは、この制度ができたのが1995年に発生した阪神淡路大震災を受けて2000年に制定された制度だったということ。
つまり阪神淡路大震災を基準として、この耐震等級という制度ができたことを知った。
でもよくよく考えてみると、数百年に一度発生すると想定された地震をベースに耐震等級が制定されたとはいえ、2000年以降でいうと震度6以上で、以下のような地震が発生している。
日本で2000年代に発生した大地震
2000年:鳥取県西部地震 震度6強
2004年:新潟県中越地震 震度7
2007年:能登半島地震 震度6強
新潟県中越沖地震 震度6強
2008年:岩手・宮城内陸地震 震度6強
2011年:東北地方太平洋沖地震 震度7
2016年:熊本地震 震度7(2回)、震度6強(2回)
2018年:北海道胆振東部地震 震度7
つまり耐震等級は、数百年に一度という阪神淡路大震災を元にして制定された制度であるにも関わらず、こんなにも多くの大地震がすでに発生しているということだった。
個人的にここで大きな2つの疑問にぶち当たった。
- 耐震等級3はあくまでも基準なので、この基準以上と考えられる建物を建てないと危ないのではないか
- これだけ多くの大地震が発生している日本において、基準値で建てればOKなんてことは無いはず
実際に調べていくと、震度7という大地震が2度も発生した熊本地震では、耐震等級2の建物の1階が崩壊したことや、耐震等級3の建物も全く無傷だったわけではなく、半壊、一部損壊という被害報告が出されていることを知ることができた。
要はこの時点で、耐震等級3の基準を満たす=安全という考えは捨てたほうが良いと思った。
さらに自分の疑問を調べていくと、次の事実を知ることができた。
その一つが地震地域係数というもの。
地震地域係数には、0.7から1.0という指数あり、地震が発生しやすい地域の基準を1.0とし、発生しにくい地域については指数を割引き0.7までを付与する。
地震が発生しにくい地域については、建物の設計時にその指数に応じて設計震度を割り引いて設計しても良いということになる。
ということは、同じ耐震等級1から3でも地域により設計上の強さが異なるということだった。
同じ耐震等級でも地域により差が発生するという、何とも意味不明な話しだ。
これにより更に耐震等級3で安心しては駄目だと強く思った。
さらに分かったことが、耐震等級3を取得する方法に2つのパータンが存在するということ。
耐震等級3を取得するための2パータンの計算方式
- 簡易計算(壁量計算)
構造にかかる風圧、地震の力に対して必要な壁量を満たすための計算方式 - 構造計算(許容応力度計算)
構造を構成する柱や壁などの強さを計算し、建物が倒壊するに至る力がどの程度などか算出する計算方式
同じ耐震等級3でも、1と2では性能が異なるということになる。
仮に同じ地域にAとBという2つの異なる建物があり、一方が簡易計算で耐震等級3を取得。
もう片方が構造計算で耐震等級3を取得しているなんてことが有り得る話で、どちらが地震に対する信頼性が高いかは一目瞭然。
よって、耐震等級3=全て同じ信頼性、同じ基準ではないということを知った。
もちろん自分の中では、2の構造計算を採用することが必須条件になった。
ちなみに木造と鉄骨で制度に差があることもここで知った。
鉄骨住宅は構造計算が必須となるが、木造住宅の場合500㎡以下、2階建て以下の場合、構造計算が不要ということ。
鉄骨が強いというイメージはここに由来しているのかもしれない。
上記以外にも色々と調べたが、大筋これらのことを知ったことにより、自分の中で耐震等級3の基準を余裕で満たす建物を探す旅が始まることになる。
耐震等級3を余裕で満たすハウスメーカー探し
耐震等級3を余裕で満たす基準を探すべく調べたのが、ハウスメーカーが独自に実施している耐震実験。
一般的に名が通っているハウスメーカーであれば、内容は多少異なれど耐震実験を実施していることが分かった。
自分が検討したハウスメーカーもやはり耐震実験をしており、実験結果を纏めると以下の通り。
住友林業
3階建で阪神淡路大震災の震度7クラス22回、震度6弱から4を224回実施したところ構造躯体の損傷がないことを確認
セキスイハイム
2階建て実験での最大加振2,112galで構造体にダメージなし
一条工務店
あらゆる地震波で揺らす実験を実施のうえ建物の強さを実証
積水ハウス
入力波最大速度160カインで建物が倒壊することなく、外壁の割れ・脱落もないことを確認
パナソニックホームズ
東日本大震災、阪神・淡路大震災などの大地震を57回、中地震83回の計140回の振動実験で、構造体の交換が必要となるような損傷が無いことを確認
ヘーベルハウス
阪神・淡路大震災の1.5倍の地震波などで繰り返し加振、構造体に大きな損傷が見られないことを確認
アキュラホーム
連続10回の耐震実験を同じ建物で実施、最大加振2,933gal、最大速度202kineで構造体と内装に損傷なし
ダイワハウス
震度6強~7阪神・淡路大震災時の記録波およびその加速度の2倍レベルも含む巨大地震を18回、大地震33回、中地震34回の計85回の加震実験で鉄骨フレームの損傷や外壁材のクラックなどの異常はなし
この調査過程で見慣れないキーワードに出会う。
gal?kine?
耐震を勉強する上で重要なキーワード「gal」と「kine」
galとは、地震の揺れの強さを表すのに用いる加速度を示す単位で、1galは毎秒1cmの割合で速度が増す加速度を指す。
ある大きさの速度に達するまでに掛かる時間が短時間であればあるほど、加速度が大きくなる。
地震が発生した際に、建物に掛かる加速度によって地震動の大きさを知ることができる。
kineとは、地震による揺れの大きさを示す単位で、1kineは1秒間に1cm動いたことを意味し、加速度に時間を掛けることで地震の強さを指す。
同じ加速度であっても、加速度の継続時間によって速度に違いが発生するため、建物にとってはgalよりも重要な指標となっている。
ということで、地震動の加速度galよりも、建物の揺れの継続時間を指すkineの方が重要であることを知った。
ちなみにgalのみでPRしているメーカーがあるものの、どのメーカーも大地震を想定してコストを掛けて耐震実験をしているため、ここはそんなに拘らなくても良いと思った。
あとは本当に信頼できるかどうかを、過去の地震でどうだったか実際に調べるだけの話し。
色々見ていくと、残念ながら大手ハウスメーカーの中には、過去の地震で倒壊しているという事実があることが分かった。
ちなみにこのメーカーについては、真っ先に候補から外した。
また中には熊本地震を経験された方の体験談がブログにアップされており、とても参考になった。
ちなみに参考になったのは、住友林業で建てたまめ八さんという方のブログ。
熊本地震での体験談を記事にされており、その体験談を見て住友林業で建てようという想いを強くした。
やはり何事も自分で調べるということは大事だ。
家は人生で大きな買い物なので、絶対に失敗したくはない。
しかも命を守るという性能面では特に。
ということで、マイホーム計画の過程で自分が勉強したこと、学んだことは下記の通り。
マイホームの耐震で検討するべき事項まとめ
・木造に関しては国の基準が甘い
・耐震等級3=すべて同じ信頼性ではない
・耐震等級の基準も地域により差が発生する
・ハウスメーカーの耐震実験は内容が異なるのでよく精査する
・過去発生した地震でどうだったかを調べる
ということ。
これから家を検討される方は、家に求める性能面で特に重要視する項目については、色々な情報を鵜呑みにせず、徹底的に調べ上げた上で判断されることをおすすめします。
自分の場合は地震に対する性能だったので、今回のような内容を徹底的に調べ上げた上で、納得の行く判断ができるようにしました。
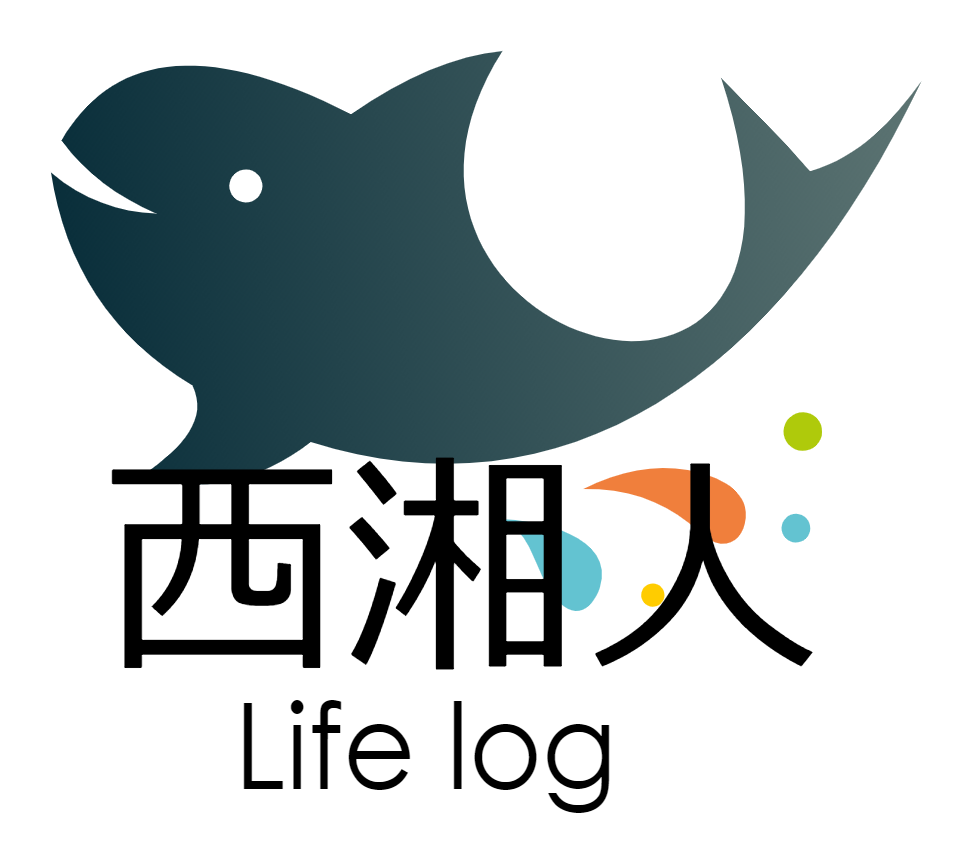


コメント